〜見通しと安心をつくる、わが家の仕組みづくり〜
🟡「構造化」シリーズ連載中!
第1弾:【構造化とは?】(このページ)
第2弾:【子どもが動けない朝】声かけいらずの支度ルールでラクになるコツ
第3弾:【視覚の構造化】子どもが自分で動ける“やることボード”の工夫
第4弾:【時間の構造化】“きりのよさ”を活かした切り替えの工夫
第5弾:【親こそ構造化】忙しい毎日をラクにする“暮らしの流れ”のつくり方
こんな悩み、ありませんか?
– 「朝の支度が毎日バトル…」
– 「“次なにするの?”が口ぐせになってる」
– 「決して手を抜いてるわけじゃないのに、暮らしが回らない…」
発達に特性のある子どもとの暮らしの中で、そんなやりとりを何度も繰り返していました。
朝の支度、学用品の準備、タブレットの使い方…
どうしても“その場の声かけ”に頼らざるを得なくて、
私も子どもも、どんどん疲れていったんです。
「構造化」との出会いは、療育の先生の一言から
わが子がASD(自閉スペクトラム症)と診断され、通い始めた療育の現場で、先生がこんなことを言いました。
「構造化で、子どもが安心して動けるようになるんですよ」
最初は正直、ピンときませんでした。
でも、家に帰ってから気になって調べてみると…
「構造化」とは、物事にルールや順番、枠組みを与えて“わかりやすくする”こと。
特別支援教育で広く使われている考え方で、特に「TEACCHプログラム」で発展してきたものです。
その1:やることを“見える化”する
朝の支度を「やることボード」に貼って、順番にこなしていけるようにしました。
文字ではなくイラストを使ったことで、子どももすぐに理解できるように。
「次何するの?」と聞かれなくなっただけで、私の朝もぐっとラクに。
その2:モノの位置を“決める”
学用品やおもちゃの置き場所にはラベルを貼り、迷わないようにしました。
戻す場所が決まっているだけで、散らかり方がまったく違うんです。
「決まっているから戻せる」=片付けの第一歩でした。
その3:ルールを“時間と場所”で区切る
スクリーンタイムのルールも、言葉だけでは伝わりにくかったので、
「時間」+「使う場所(例:リビングだけ)」で明確にしました。
ルールが“見てわかる”状態になると、トラブルも激減!
構造化は、すべての子にやさしい工夫だった
やってみて感じたのは、構造化は特別な支援ではなく、誰にとってもわかりやすくなる工夫だということ。
- 年齢に関係なく、「見てわかる」「決まっている」は安心できる
- 声かけの頻度が減り、親のイライラも減る
- 子どもが“自分でできた”という経験を積みやすくなる
構造化=暮らしの“見通し”をつくるヒントなんだと思いました。
「構造化」は、発達支援だけのものじゃない
発達障害の子どもたちのために生まれたこの考え方だけど、
私自身はこう思っています。
「発達障害の人にとってわかりやすいことは、誰にとってももっとわかりやすくなる」
毎日バタバタしてしまう…
つい子どもにイライラしてしまう…
何から片付けたらいいのかわからない…
そんな暮らしのモヤモヤを、
ちょっとした「構造」でほぐしていけたら——
わが家では、それができたことで、家族みんながぐっと暮らしやすくなりました。
まとめ
もし今、「暮らしがなんとなく回らない」と感じていたら……
まずは“見てわかる”しくみを一つだけ、取り入れてみてください。
ポスターでも、配置でも、ラベルひとつでも。
それがきっと、あなたの家の「暮らしを整えるはじめの一歩」になりますよ🍋
📌この記事を読んだ方にはこちらもおすすめ
・【子どもが動けない朝】声かけいらずの支度ルールでラクになるコツ
・【視覚の構造化】“やることボード”の工夫で自分から動けるように
・【親こそ構造化】暮らしの流れを整えてみた話

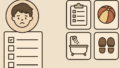
コメント